阪井裕一郎氏に拠る『結婚の社会学』(2024年4月刊・ちくま新書)という書。
その「第2章 結婚の現代史」<5 マッチングアプリ時代の結婚を考える>の内容と、他の2つの調査結果を参考に、前回、以下の記事を投稿しました。
⇒ マッチングアプリ婚活のリアル|デジタル時代の結婚をデータと社会学で読み解く – 結婚家族.com
本稿は、それを受けて、マッチングアプリの利用が浸透して実現した「デジタル化した婚活」について考えてみます。
ページに広告が含まれることがあります。
デジタル婚活の現在と明日|少子化時代における結婚のリアルと課題
現代の日本社会において、「結婚」に至る人の数そのものが年々減少しているという現実があります。
本記事では婚活のデジタル化に焦点を当てます。しかし、その前にまず「婚活以前の問題」として、結婚そのものがしづらくなっている社会的背景を押さえておきたいと思います。
そもそも日本における婚姻数自体が減少傾向にあるという事実に目を向けておく必要があります。
マッチングアプリや結婚相談所といった婚活手段がどれだけ多様化・高度化しても、それを利用する人が減っていけば、婚活市場そのものが縮小してしまいます。
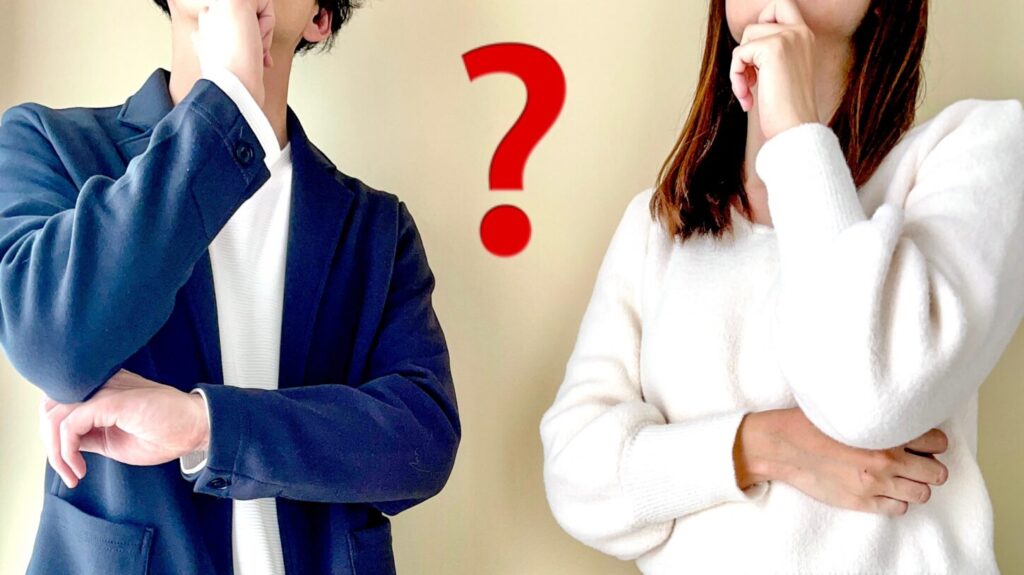
婚姻数の減少とその背景
実際、厚生労働省の「人口動態統計」によれば、婚姻件数は1970年代以降ほぼ一貫して減少。2020年代に入ってからは特に顕著です。
コロナ禍の影響も重なった2020年の婚姻数は戦後最少の52万組を記録し、その後も回復する兆しは見えていません。
その背景には、単に恋愛や婚活の問題だけではなく、長期的に進行する少子化、経済的な不安、そして若年層の都市集中による地域間の人口格差といった構造的な要因が複雑に絡み合っています。
これが、結婚というライフイベントに大きな影響を与えているのです。
それらの要因について、以下簡単に整理してみました。
長引く経済停滞と若年層の不安
バブル崩壊以降、日本は長く低成長・低所得時代が続いており、特に若年層の所得水準の伸び悩みが深刻です。
非正規雇用の増加やキャリアの不安定さが影響し、将来への見通しを持ちにくくなった。
そのため「結婚をする」「結婚して子どもを持つ」「家庭を持つ」という選択に慎重になる傾向が強まっています。
特に男性側において、「経済的に結婚に踏み切れない」と感じる層が増えているという調査結果もあります。
地方の過疎化と出会いの機会の減少
また、地方から都市部への人口集中も結婚機会の偏在を招いています。
若者が地元を離れて進学・就職する中で、地元での出会いの機会が激減。
結婚適齢期を迎えても自然な出会いが難しくなっています。
さらに、都市部ではライフスタイルの多様化とともに、個人主義的な価値観が浸透し、結婚を急がない・望まない層も増えています。
その背景には、地方に魅力的な仕事が少ないという事情もあります。
こうした社会的背景は、結果的に「結婚のタイミングを逃す」若者を増やしていると言えるでしょう。
価値観の多様化と独身志向|強まる非婚化、晩婚化
加えて「結婚しない人生」や「一人で生きることへの肯定感」が広がってきた。これも、婚姻数の減少に影響しています。
特に「結婚=人生の必須ステップ」という価値観が崩れつつある中、30代以降の未婚率が高まっています。
結婚に対する動機そのものが希薄化している証とも指摘されています。
即ち、「結婚=幸せ」という価値観自体が見直される中、「一人でも充実した人生を送る」「無理に結婚しない」。
その選択が広がったわけです。
それにより、結婚をしない人・結婚を遅らせる人が増えている。
非婚化や晩婚化です。
こうした構造的・社会的な背景を踏まえると、単に「出会いの場が足りない」から結婚が難しい。こう単純に結論付けるればよいというものではありません。
婚活を考える以前に、結婚に至る社会的基盤、根本的な環境そのものが揺らいでいる。
それが現代日本の実情です。

婚活のデジタル化がもたらした変化
マッチングアプリが当たり前に
スマートフォンとSNSの普及により、出会いの手段は急速に変化しました。
かつては「結婚相談所」や親族主導や地縁型の「お見合い」が主流でした。
しかし、今ではオンラインマッチングが一般化。多くの若者が、そしてミドル世代にも及び、マッチングアプリを活用しています。
マッチングアプリの普及は、出会いの場を拡大しただけではありません。恋愛や結婚への考え方にも新しい価値観をもたらしました。
例えば、以下のようなメリット、特色を持つようになってきました。
1)地理的な制約を超えた出会い
居住地に関係なく、全国の人と出会える機会が広がっています。
2)趣味・価値観重視のマッチング
プロフィールや興味の一致を通じて、内面的な相性を重視する出会いが可能になっています。
3)自分のペースで婚活ができる
忙しい日常の中でも、自分の都合に合わせて婚活を進められる柔軟性があります。
4)行動データに基づく最適化された相手選び
AIが閲覧履歴や好みを分析し、より相性の良い相手を提案する仕組みが整いつつあります。
気になるのが、趣味・価値観重視のマッチングと行動データに基づき最適化された相手選び。
例えば、地理的な制約を超えた出会いは、仕事の場と実際にどこで暮らすかという問題。乗り越える必要があります。
要素・条件をクリアできる出会いが、双方の価値観のすり合わせにより可能になるでしょうかかもしれません。
しかし、自分のペースで婚活ができるかどうかは、相手次第でもあります。
マッチングアプリのデメリット|個別最適化と選択疲れのジレンマ
この問題も含め、マッチングアプリのデメリット・課題を整理しました。
1)豊富な選択肢による「選択疲れ」
選択肢の豊富さは魅力である一方、選べない、決められないという「選択疲れ」を招くこともあります。
2)見た目や条件など「偏重傾向問題」
第一印象が写真やプロフィールに左右されやすく、見た目や条件偏重になりやすい傾向も問題視されています。
そのため、マッチングが決まる可能性が狭められるわけです。
3)メッセージのやり取りが続かない「メッセージ疲れ」
文章中心のやり取りが長引き、実際のデートに進みにくくなる傾向があります。
4)次々と新しい相手と出会えることで関係が深まりにくい「無限ループ問題」
次の候補が常に現れるため、一人との関係をじっくり築く意識が希薄になりやすくなっています。
このように、婚活がデジタル化することで、便利になる一方で新たな心理的負荷も発生しているのです。
婚活サービスの進化と社会の変化
婚活が特別ではなく「普通」に
少し前までは「婚活するなんて必死に見える」「恥ずかしい」といった感覚が根強くありました。
しかし現在では、婚活サービスを利用すること自体が当たり前に誰もが気軽に始められる時代となっています。
それぞれのニーズに応じた、次のような多様なサービスも整っています。
1)マッチングアプリ(Pairs、Omiaiなど)
スマホひとつで始められる手軽さがあり、特に若年層に広く利用されています。
2)結婚相談所(IBJなど)
カウンセラーのサポートを受けながら、真剣に結婚を考える人が登録しています。
⇒ いま話題の婚活ビジネス【IBJ】
⇒ 初めてでも安心して活動できる結婚相談所【エン婚活エージェント】
3)婚活パーティー(ゼクシィ縁結びPARTY等)
実際に顔を合わせて話したい人に向けて、リアルな場を提供しています。
⇒ IBJ Matching(旧PARTY☆PARTY)で結婚しよう!
⇒ 初めての方でも安心して参加できる婚活パーティーです|おとなの婚活パーティーOTOCON(おとコン)イベント・パーティー)
4)オンライン婚活イベント(ZOOM婚活等)
非対面でも雰囲気を感じられる仕組みで、忙しい人でも参加しやすくなっています。
⇒ オンラインAI恋活・婚活【Sunday Nine】
AIが導く新時代のマッチング
婚活業界では、AIを活用した高度なマッチング技術が進化を続けています。
人間の行動データや趣味・価値観の分析に基づくレコメンドが可能となりました。従来よりもマッチングの精度が格段に向上しています。
代表的な技術例を以下にメモしました。
1)AIによる相性診断
プロフィール情報やアプリ内の行動履歴から、相性の良い相手を分析して推薦します。
2)自動メッセージ作成支援
過去の返信率の高いメッセージデータをもとに、効果的なやり取りをサポートします。
3)不審ユーザーの検出と通報
AIが不審な動きを検出し、安全性の高い婚活環境を提供しています。

デジタル婚活のこれからと活用のポイント
技術革新が拓く新たな婚活体験
今後、次のような技術の進展によって、婚活の形はさらに多様化していくことが予想されます。
1)VR婚活
仮想空間を通じてリアルなデート体験を提供します。これにより、物理的な距離を超えて親密さを育むことができます。
2)ブロックチェーン婚活
本人確認の信頼性が高まり、身分詐称などのリスクが大幅に軽減されます。
3)遺伝子マッチング
遺伝子レベルでの相性診断により、より科学的根拠のあるマッチングが期待されます。
こうした例は、デジタルライフにおける高度なデジタル化が、婚活に大きな影響を与える要素と言えます。
(参考) デジタルライフとは?LIFE STAGE NAVIにおけるカテゴリー設定の背景と今後の展望 – LIFE STAGE NAVI
デジタル婚活への反動も|リアル婚活回帰もあり?
テクノロジーの発展と並行して、アナログな出会いを求める反動も出てきています。
「デジタルデトックス婚活」「リアル婚活回帰」と言われるような傾向です。
この状況は、婚活サービスやサポートにおいて、多様なニーズへの対応が必要であることを示しています。
例えば、最近では、企業内福祉として社内恋愛や社内結婚、社内婚活を支援する動きも紹介されています。
注目したいです。
こうした例についても、別の機会に紹介したいと思います。
婚活サービスを選ぶ際のポイント
婚活の成功には、自分の目的に合ったサービスを選ぶことが重要です。
以下の観点から、利用するサービスを選びましょう。
1)目的に応じた選択
たとえば、
・気軽な出会いを求めるならマッチングアプリ
・結婚を真剣に考えているなら結婚相談所
・直接会って話したいなら婚活パーティー
など、目的に応じたサービスを選ぶことが効果的です。
2)安全性の確認
身分証明や本人確認のプロセスがしっかりしているか、運営元が信頼できる企業かどうかをチェックしましょう。
3)複数併用の工夫
マッチングアプリと結婚相談所を併用するなど、複数の手段を組み合わせることで出会いの幅を広げることができます。
まとめ|婚活サービスをどう使いこなすか
婚姻数が減少し、結婚そのものが難しくなっている時代。
デジタル婚活は新たな希望の選択肢として注目を集めています。
マッチングアプリやAI技術の活用によって出会いのチャンスは拡がっています。
しかし、先述したように、情報過多や選択疲れといった課題も浮かび上がっています。
これからの婚活では、「どのサービスを使うか」、「どのように使いこなすか」が重要になります。
テクノロジーを味方にし、自分の価値観や目的に合った婚活スタイルを見つけていく。
それが、希望を実現する上でのポイントになるでしょう。
今後は、各種婚活サービスの具体的な内容や機能、料金体系、実際の利用者の声なども紹介。
実践的・現実的な活用法を含め、ライフステージ、ライフスタイルに応じた情報と考察をお届けします。

前回記事の再確認は、こちらからできます。
⇒ マッチングアプリ婚活のリアル|デジタル時代の結婚をデータと社会学で読み解く – 結婚家族.com
コメント