総括:子育て支援政策の経済統計および経済対策からのアプローチ|その意義と疑問
「EBPM (Evidence-Based Policy Making)、実証結果に基づく政策形成」という用語を、最近は頻繁に見かけます。
いたずらに、むやみに政府財源を政策に投入することを戒め、実証・検証結果に基づき、有効に予算化・投入計画化すべき、という主張です。
柴田氏の両書もそれに基づいての提案・提言書でした。
データに基づく政策主義・EBPMの疑問と数字のマジック
しかし私は、EBPM主張には、現状の数に依拠した自民党の多数決強権民主主義政治と同根の匂いを感じます。
本書の課題による統計データ分析は、もともとゼロの段階から企画実施した保育関連事業の計画ベースでの仮説・検証というマネジメントサイクルに基づくものではありません。
そうでなく、過去の数字の実績・実態集計の分析であり、本質的な仮説ではなく、積み上げられた過去データに基づく仮説です。
しかもデータ分析における条件は、多様に絡む諸要素を取捨選択・捨象して、極力単純化して分析するものです。そのため、却って加工度が高くなっているという問題があると考えます。
そして、多数の陰に隠れている少数のデータ、数値が取り上げられない可能性が高いことは、現状の民主主義と変わらないところです。
しかも、統計的分析の基準・指標として用いるのがOECDデータ。
最もポピュラーで、オフィシャルな手法ではあります。しかし、基本的に、他の国がどうだから、その平均・標準から乖離しているから、などと問題を蓋然化する方法にも疑問を感じます。
もちろん理想とすべき事例・モデルを得て、それを目標とすることがいけない、まずいとするものではありません。方法を学ぶことは大切ですが、日本独自にモデル化を図るという視点が大切と考えるのです。
また、コンマ以下の数値を用いての比較評価では、いとも簡単に成果や波及効果の度合いが数倍、数十倍、数百倍に換算・転換されます。これにより過大評価・過小評価化され、数字のマジックゲームが繰り広げられ、実態を見えにくく、間違いやすくするのです。
本書が掲げる「政策効果の統計分析」が本質的に持つ課題をしっかりと認識した上で、読み取り、活用する必要があります。
書籍カバー帯の2著名人駒崎弘樹・古市憲寿氏の言への疑問
社会保障について提案・提案するときには、財政面からの提案が不可欠。
駒崎氏とのコミュニケーション時にアドバイスされたこの言で、本書のような性格の書が誕生したことを柴田氏が、新書のあとがきに記しています。
駒崎弘樹氏:子どもと子育てへの投資は、経済成長をもたらす。本書は、日本の少子化と待機児童問題を解決するバイブルだ!
財源ありき、経済ありきの考え方は、種々の活動に携わり、政府や行政とのコミュニケーションの機会が誰よりも多い民間実務家である駒崎氏が日々実感としていることは充分理解できます。
しかし、社会保障が、所得再分配システムに依存しなければいけないという発想とは、そろそろ袂を分かつべきではないでしょうか。
義務教育が財政・財源云々とは決してされないように、保育も同じジャンルの行政課題であるからです。
すなわち、経済成長やGDPの拡大、労働生産性向上、そのための女性就労率向上という付帯条件とその議論の必然から解き放つべきと考えます。
もう一つ、「帯(おび)」の内容を紹介します。
古市憲寿氏:こんな本を待っていた! なぜ子育て支援が重要なのかを統計的に実証。今後、日本の政策立案は本書抜きでは語れない。
同根の認識にあるこの意見も、学者にありがちな、数値結果が先かプランが先か、の不毛の形式に縛られた堂々巡り。それに終わってしまうことが関の山です。
古市氏は、柴田氏が本書を発売する前年に『保育園義務教育化』(2015/7/6刊・小学館)を発刊。
柴田論に先行して、この書で待機児童問題や少子化問題について論じ、保育園の義務教育化がそのどちらにも有効としての提案でした。
古市氏はそこでは、「「義務教育」にはみんなが従う」とし、財源がどうこうなどと言っていません。
その彼が、学者の本領でしょうか、そこかしこでEBPMを喧伝していることにはどうも賛同できないのですが。
そのモデルとすべき実証研究として、EBPM主張のほとんどすべての研究者が利用しているのが、極端な理想環境設定に基づくことで有意性が当然である「ペリー幼稚園プログラム」。
もうそろそろ紋切り型・活用たらい回し型のEBPMは、遠慮すべきと思っています。
ベーシックインカム機能を持つ児童手当と子育て支援・少子化対策を包括するベーシック・ペンション
『子育て支援と経済成長』<第3章>の「児童手当」に関する記述から
基本的に、財政規律主義、税と社会保障の一体改革に従っての子育て支援策・少子化対策を、誠実に、突きつめて考察する柴田氏。
そのためには相当の財政出動が不可欠とみ、社会保障の拡充には経済成長が条件とする立場です。
ですから、ベーシックインカムを用いそれらの政策に充てるという発想は持ち得ないでしょう。
しかし、実は、新書の方に、興味深い箇所・記述があります。
「児童手当」についての経済学者アンソニー・アトキンソンの考えを以下のように引用しているのです。
「すべての子ども(の養育者)に対して、児童手当を十分に給付し、その給付金額を所得税の課税対象に含めれば、結果的に、貧困家庭の子どもに焦点を絞って、救済することができる。」と提案。
不安定雇用が増加した現代において、このような児童手当、いわば子どもを対象としたベーシックインカムこそ、社会保障制度の中心に据えるべきだと、提言しているのです。
柴田氏は、どういう気持ちからこの引用を行ったのでしょうか。
児童手当自体がベーシックインカム。
まさにすべての児童に無条件に、平等に支給するものですから、児童へのベーシックインカム。
私が提案するベーシック・ペンションは、包括的には「生活基礎年金」と呼びますが、児童に対する生活基礎年金は「児童基礎年金」と呼ぶことにしています。
この絡みでは、専門サイト http://basicpension.jp で触れています。
今後の社会学者柴田氏への期待と限界?
さて、少子化問題とその対策には、柴田氏の2書において、さほど力が入っていないようでした。
経済を軸にすれば、自ずと少子化対策が、優先すべき順に位置付けられると思うのですが。
また子育て問題の現実を考えると、統計や経済的効果云々よりも、非正規労働・雇用問題や賃金問題育児・介護休業制度などの内容や運用問題などが、当然課題にされ、踏み込みが必要になります。
それらは柴田氏が理想とし、必然とする、与野党の壁を乗り越えた共通認識・共通課題として取り組むべき課題です。
しかしそれも財源・財政の考え方の根本的な違いを超克する共通課題であり、合意形成可能な提案に至るならば、具体化されてしかるべきなのですが、その兆しはありません。
となると政治によりコンタクトするか、政策提案により磨きをかけるか。
どちらにしても、社会保障制度は、子育て・保育問題だけで留めることは不可能です。
子どもや障害者への社会保障財源の支出が、対高齢者等に比較して少ない、という認識から始まった論述ならば、必ず、子ども・障害者以外のその在り方についても提起・提案すべきことは言うまでもありません。
社会学と社会保障論を専門とするからには、避けて通ってはいけない課題。
今後の活動に期待したいものです。

本稿と関連した内容の以下の記事も参考に。
◆ 紋切り型<社会保障の経済・財政との一体改革>論から脱却してベーシック・ペンションを:日経経済教室「社会保障 次のビジョン」から-1(2022/3/11)
ベーシック・ペンションの2022年版についての提案は、以下のラインアップで確認いただけます。
(参考)
◆ ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16)
◆ 少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2(2022/2/17)
◆ マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3(2022/2/18)
◆ 困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4(2022/2/19)
参考:『子育て支援が日本を救う 政策効果の統計分析』構成
はじめに
第1章 本書の問いと答え ー 子育て支援が日本を救う
1.労働生産性を高め財政を健全化させる政策
2.自殺を減らす政策
3.子どもの貧困を減らす政策
4.財源確保の方法
5.日本の「現役世代向け社会保障」が乏しい背景
6.「選択」は「歴史」をのりこえる
第2章 使用データと分析方法
1.使用データの概要
2.分析方法 ー経済成長の研究から学ぶ
3.経済成長とは何か
4.経済成長率の先行研究
5.説明変数と被説明変数
6.最小二乗法推定(OJS推定)
7.パネルデータ分析でのOLS推定 ー動学的推定と一階層差推定
8.「逆の因果」の除去 ー操作変数推定
9.すべてを兼ね備えた一階層差GMM推定
10.一階層差GMM推定の手続き
11.実際上の留意点
12.使用データについての留意点
第3章 財政を健全化させる要因 ー労働生産性の向上
1.背景 ー財政難という問題
2.仮説
3.データと方法
4.結果
5.結論
第4章 労働生産性を高める政策 ー女性就労支援・保育サービス・労働時間短縮・起業支援など
1.背景 ー「労働生産性の向上」は財政健全化をもたらす
2.仮説
3.データと方法
4.結果
5.結論
第5章 女性の労働参加を促す政策 ー保育サービス・産休育休・公教育
1.背景 ー「女性の労働参加」は「社会の労働生産性」を高める
2.仮説
3.データと方法
4.結果
5.結論
第6章 出生率を高める政策 ー保育サービス
1.背景 ー「出生率の向上」は財政健全化をもたらす
2.先行研究で残された課題
3.仮説
4.データと方法
5.結果
6.結論
第7章 自殺を減らす政策 ー職業訓練・結婚支援・女性就労支援・雇用奨励
1.背景 ー自殺率という問題
2.先行研究で残された課題
3.仮説
3.データと方法
4.結果
6.結論
第8章 子どもの貧困を減らす政策 ー児童手当・保育サービス・ワークシェアリング
1.背景 ー子どもの貧困という問題
2.仮説
3.データと方法
4.結果
5.結論
第9章 政策効果の予測値
1.予測値の計算方法
2.OECD平均まで拡充する場合の予算規模と波及効果
3.待機児童解消に必要な予算規模
4.その場合の波及効果
5.他の目標のための予算規模
6.結論 ー現実的な目標設定と予算規模
第10章 財源はどうするのか ー税制のベストミックス
1.行政コストの削減には限界がある
2.財政方式をどうするか
3.個人所得税・社会保険料の累進化
4.年金課税の累進化
5.被扶養配偶者優遇制度の限定
6.消費税の増税
7.資産税の累進化
8.相続税の拡大
9.相続税拡大だけならベルギーの1.2倍
10.小規模ミックス財源
11.最小限の改革 ー潜在的待機児童80万人の解消
第11章 結論 ー子育て支援が日本を救う
1.右派「保守」と左派「リベラル」の合意点
2.残された課題
あとがき
参考:『子育て支援と経済成長』構成
はじめに
第1章 財政難からどう抜け出すか
・お金がないのが大問題
・日本政府の懐事情
・社会保障支出に食いつぶされる超高齢社会・日本
・訪れなかった第3次ベビーブーム
・先進諸国の経験から学べ ー統計分析という手法
・財政余裕に影響する三つの要素
第2章 働きたい女性が働けば国は豊かになる
・財政余裕は改善できる
・女性の心に響く商品を生み出すには
・正社員女性比率と利益率
・ラガルド発言の根拠
・「財源なし」でできる一手
・そもそも昔の女性は働きに出ていた
・女性の職場進出を後押しする
・「3年間抱っこし放題」は効果なし?
・育休より効果的な保育サービス
・保育の拡充が財政余裕を増やす?
・限られた予算を活かす政策を
第3章 「子どもの貧困」「自殺」に歯止めをかける
・高齢者より高い子どもの貧困率
・子どもの貧困がもたらす問題
・子どもの貧困を減らす政策
・ワークシェアリングより保育サービス
・家計に負担のかかる無認可保育園
・3歳以上は夕方まで保育無料のフランス
・児童手当も大事
・日本の自殺率を下げる
・自殺予防に効果的な政策
・離婚による孤独と自殺
・「一家の大黒柱」からの解放
・子育て支援が日本を救う
・それぞれが「幸せ」を感じられる社会
第4章 社会保障の歴史から見るこれからの日本
・子育て支援額は先進国平均の「半分」
・「経済成長を促す政府支出もある」
・障害者福祉サービスと「応益負担」
・「適応」って本当にいいことなの?
・適応概念の歴史
・社会保障の問題を数字で示したら
・高福祉国家・北欧とルター派の関係
・宗教改革が高福祉国家を生んだ
・17世紀に導入された救貧税
・カルヴァン派がつくった低福祉国家・アメリカ
・投資によって偶然儲かったら
・キリスト教の歴史と社会保障
・トッドの家族システム論
・日本はなぜ低福祉になったのか
・江戸時代からの新しい救貧文化
・バブル崩壊後の企業福祉
第5章 子育て支援の政策効果
・結局、待機児童はどれくらいいるのか
・子どもを持ったお母さんは一生パート?
・保育士が集まらない
・待機児童問題解消にはいくら必要か
・公立の認可保育所は縮小傾向
・子育て支援でどのくらい経済成長するのか
・待機児童解消による政策効果
・長時間労働が引き起こす「保育の質」の低下
・フランス革命と出生率
・保育ママ以外の要因は?
・フランスから学べること
・保育所で解決したスウェーデン
・「マツコ案」で保育・教育の無償化を試算してみた
第6章 財源をどうするか
・財源のミックス案
・財源案の合意形成に向けて
おわりに ー分断を超えて
・古市さん、駒崎さんとの出会い
・相手と共通の「暗黙の前提」からスタート
・子どもたちのための協力
2025年の「少子化社会」問題への取り組み
再掲に当たって、読みなおしての感想や思いをここで綴るべきかとは思いましたが、当サイトは始まったばかり。
一応、この記事のテーマについての基本は書き記していると思います。
しかし、これから、2025年における少子化対策の変化と動向を追っていく中で、柴田論に後述する山口論も加えて、見直すことにしたいと思います。
なお現在日本を代表する研究者である彼ら。時々寄稿しいる日経等にも常に注目し、その内容は紹介したいと思います。

なお、EBPMの書としてはもちろん、子育て支援政策そのものとして、柴田氏論の後に執筆・発行された、経済学者山口慎太郎氏の書についても、別途紹介と論述をと考えています。
(参考): 山口慎太郎氏著
・『「家族の幸せ」の経済学 データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』(2019/7/30刊・光文社新書)
・『子育て支援の経済学』(2021/1/20刊・日本評論社)
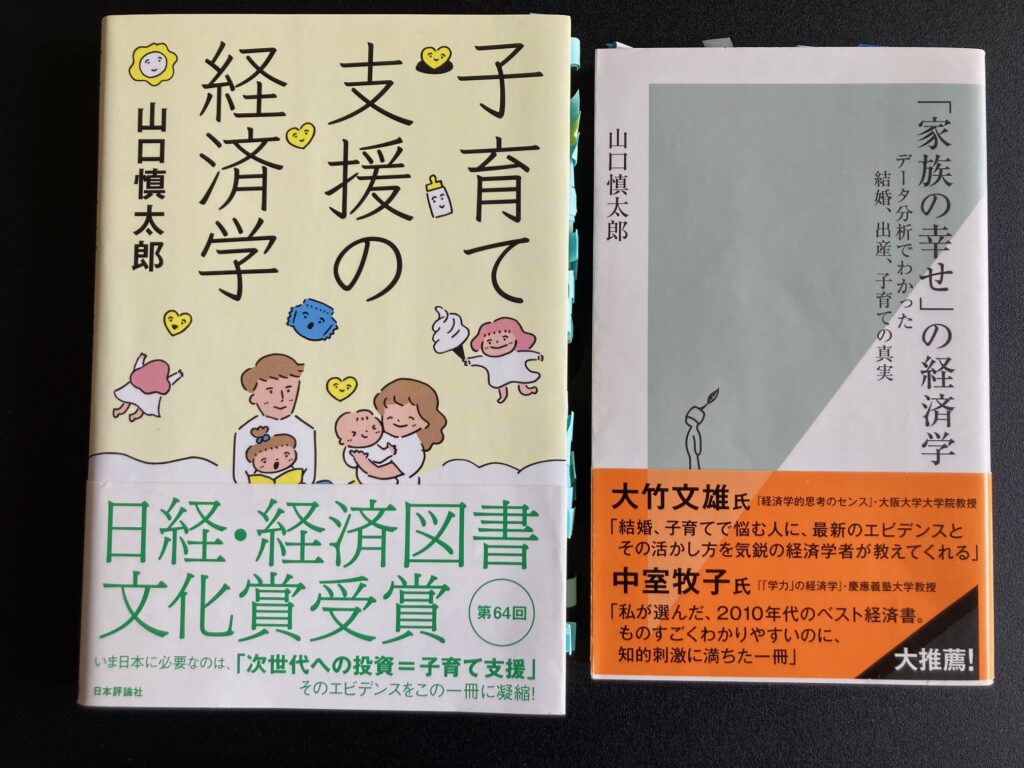
前回のデジタル婚活についての記事は、こちらです。
⇒ デジタル化する婚活、これからの期待と不安 – 結婚家族.com
コメント