再三の昨年の情報で恐縮です。
2024年11月13日、14日に「令和の結婚観」というテーマで日経に、以下の記事が掲載されました。
⇒ 令和の結婚観(上)年上の妻、増え続ける 互いに経済力求める 少子化対策に穴 – 日本経済新聞
⇒ 令和の結婚観(下)老後の「おひとりさま」増 熟年離婚、昨年23%最高 資産形成や年金改革が必須 – 日本経済新聞
旧き昭和の時代との違いは、あって当然です。
しかし、平成と令和の間に、「結婚観」に大きな違いがあるのか、どうか。
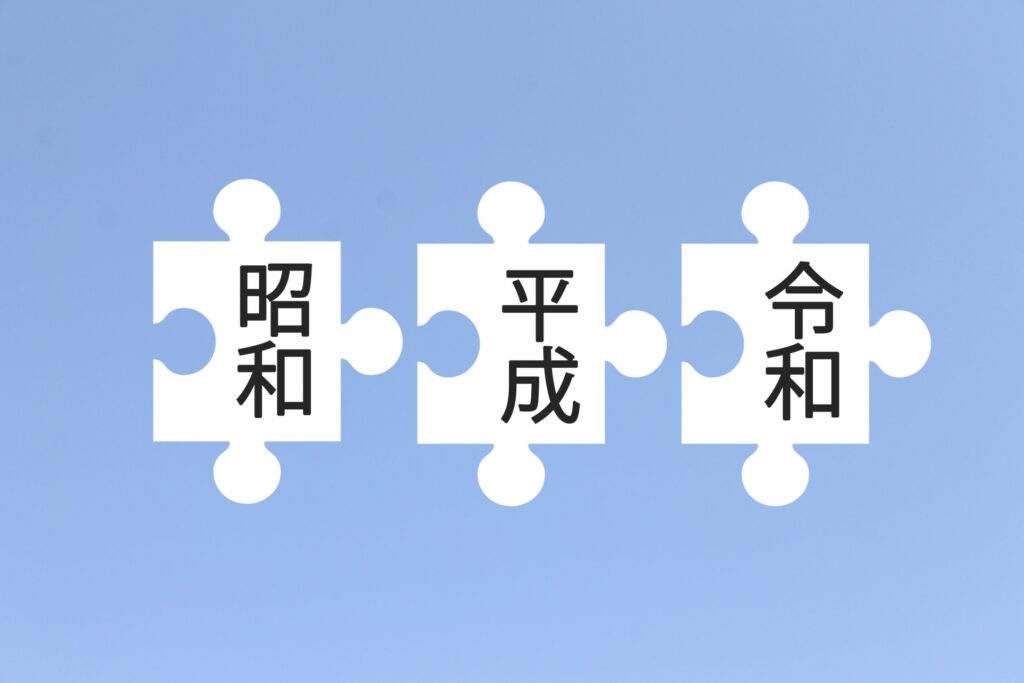
その内容を令和7年の今、確認してみることにしました。
試みにやってみたのが、生成AIである、ChatGPTとDeepSeekに、2つの記事と要約を「令和の結婚観とこれからの課題」と題してまとめてくれるよう依頼。
その内容を、ChaTGPT、DeepSeekの順に掲載します。
(この作業を行ったのは、今年2月です。)
初めは、ChatGPTのよるレポート。
令和の結婚観とこれからの課題(by ChatGPT)
1. 変化する結婚観:年上の妻、互いの経済力を重視
かつては「夫が年上、妻は年下」「結婚は勢い」といった価値観が一般的だった。しかし令和に入り結婚観が大きく変化している。
厚生労働省の人口動態統計によると、2023年には初婚同士の夫婦の24.8%が妻が年上。特に20代男性の場合、年上の妻を選ぶケースが3割を超えるまで増加。
背景には、男女ともに結婚相手に経済力を求める傾向が強まっていることが挙げられる。
2021年の調査では、結婚相手の女性の経済力を「重視する」と答えた独身男性は48.2%。2002年から19ポイントも上昇。かつて主流だった専業主婦志向は6.8%にとどまる。共働きで家庭と仕事を両立する夫婦像が支持されている。
また、年収の高い女性が結婚しにくい時代は終わり。年収が高いほど未婚率が低くなる傾向が確認されている。
2. 結婚難の時代と少子化問題
お互いに経済力を重視することで、条件に合う結婚相手を見つける難しさが増している。
日本では婚外子が少ないため、結婚数の減少がそのまま少子化に影響を与えている。
石破首相は「少子化の本質は『少母化』だ」と指摘。結婚できない若者への支援が必要だと訴えている。
しかし、こども家庭庁が結婚支援センターへの交付金などに計上の53.2億円。だが、抜本的な改善にはつながっていない。また、2022年度には結婚支援センターの利用で成婚したカップルはわずか1698組である。
3. 熟年離婚の増加と背景
結婚生活が長年続いた夫婦でも離婚に至るケースが増えています。2023年の熟年離婚率は23.5%と過去最高を更新しました。毎年約8万人の熟年離婚者が「おひとりさま」となっています。離婚の理由には、モラルハラスメント(モラハラ)などの問題や「次の人生を楽しみたい」というポジティブな動機も増えています。
また、2008年には専業主婦を対象とした年金分割制度が導入され、財産分与と合わせて経済的不安がある程度軽減されるようになりました。しかし、経済的な不安以上に、積年の不満や孤独感が離婚を決断させるケースも多いとされています。
4. 増加する単身高齢者と資産形成の必要性
生涯未婚率も上昇しており、2020年には男性28.3%、女性17.8%が50歳時点で未婚という結果が出ています。加えて、2050年には65歳以上の単身世帯が1083万人に増え、全世帯の2割を占めると推計されています。こうした背景から、高齢者の孤立や生活の質の低下が懸念されています。
単身世帯の増加に伴い、年金制度の見直しも進んでいますが、現状では公的年金だけでは老後の生活を支えるには十分とはいえません。50歳男性が65歳で受け取る公的年金の平均額は月15.6万円、女性は10.9万円にとどまります。公的年金に加えて、企業年金や個人年金(iDeCoなど)による私的年金の重要性が増しています。政府は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入年齢上限引き上げなど、年金制度改革を進めていますが、家族構成の変化に対応した柔軟な資産形成が引き続き求められています。
5. 結婚と老後問題を結びつけた社会改革の必要性
令和の結婚観の変化により、夫婦間の在り方や結婚の意味が多様化する一方、結婚難や少子化、高齢者の単身化といった社会課題も浮き彫りになっている。これらを解決するためには、結婚支援だけでなく、家族を前提としない個人単位での社会保障や資産形成の支援が必要です。
政府による年金制度の改革や私的年金の活用促進に加え、地域コミュニティを活用した孤立防止策の強化が急務といえよう。結婚観や家族観の多様性を尊重しつつ、現代の課題に対応した社会改革が今後の日本にとって不可欠である。

次は、DeepSeekによるまとめです。
令和の結婚観とこれからの課題(by DeepSeek)
1. 令和時代の結婚観の変化
令和時代の結婚観は、従来の「夫は年上、妻は年下」「夫は外で働き、妻は家庭を守る」といった伝統的な価値観から大きく変化している。特に、以下のような傾向が顕著である。
・年上妻カップルの増加:2023年に結婚した初婚同士の夫婦のうち、24.8%は妻が年上で、過去最高を更新。特に20代男性では、年上の妻を持つカップルが3割を超える。
・経済力重視の傾向:男女ともに結婚相手に経済力を求める傾向が強まっており、独身男性の48.2%が女性の経済力を「重視・考慮する」と回答。男性が女性に求める生き方として、「結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける」が39.4%でトップとなり、専業主婦を希望する割合は減少。
2. 少子化対策の難しさ
婚外子が少ない日本では、結婚する夫婦が増えなければ少子化傾向は反転しにくい。政府や自治体は若者の結婚支援に力を入れており、2025年度予算で53.2億円を計上したが、2022年度の結婚支援センターでの成婚率は0.3%と低い。岸田前政権の「異次元の少子化対策」は子育て世帯の支援が中心で、未婚者への対策が不十分との批判もあった。
3. 熟年離婚の増加と単身高齢者の増加
・熟年離婚の増加:2023年の離婚件数に占める熟年離婚(20年以上の婚姻期間を経た夫婦の離婚)の割合は23.5%と過去最高を記録。離婚件数自体は減少しているが、熟年離婚は2000年ごろから4万件前後で高止まりしている。
・単身高齢者の増加:国立社会保障・人口問題研究所(社人研)によると、50歳時点で一度も結婚をしたことがない人の割合は、2020年に男性で28.3%、女性で17.8%に達した。2050年には65歳以上の単身世帯が1083万人と、2020年から47%増える見込み。
4. 経済的不安と年金制度の改革
・経済的不安:厚生労働省の財政検証結果によると、現在50歳の男性が65歳で受け取る平均年金額は月15.6万円、女性は同10.9万円。公的年金だけでは老後の生活を支えるのが難しい。
・年金制度の改革:政府・与党は2024年末までに年金制度改正法案をまとめる予定。厚生年金のパート労働者への適用拡大などによる年金額の底上げ策を検討中。また、企業年金や個人年金といった私的年金で自己資産を厚くし、老後の生活資金を補完する必要性が高まっている。
5. 今後の課題
・結婚支援策の強化:新しい結婚観を踏まえた上で、結婚を個人の自由な意思決定としつつ、結婚支援策を強化する必要がある。特に、未婚者への対策や成婚率向上に向けた具体的な施策が求められている。
・社会保障制度の見直し:単身高齢者の増加に伴い、老後の生活設計や社会保障制度の見直しが急務。年金制度の改革や個人の資産形成を支援する政策が重要。
・社会の意識改革:離婚は回避すべきだという風潮が薄れ、個人の選択が尊重されるようになったが、単身高齢者の経済的不安を解消するための社会全体の意識改革も必要。
結論
令和時代の結婚観は、年上妻や経済力重視の傾向が強まり、伝統的な結婚像から大きく変化している。
少子化対策においては、結婚支援策の強化が求められるが、その効果はまだ不透明だ。
また、熟年離婚の増加や単身高齢者の増加といった新たな課題に対応するため、年金制度の改革や個人の資産形成を支援する政策が不可欠である。
政府や社会は、新しい結婚観を踏まえた上で、結婚を支援するための新たなアプローチを模索する必要がある。

日経「令和の結婚観」企画の目的
元々は、2月3日に投稿した記事を、当サイトを開設したことで、こちらに移行しようと。
その改訂版をと始めたのですが、今年2025年元旦付で日経が、
「一年の始まりに考える「令和の結婚観」 – 日本経済新聞」と題した情報を発信。
その冒頭のコメントを整理してみました。
人生観や家族観は変化している。
男女ともに結婚相手に対して経済力を求めるようになった。
「熟年離婚」は全体の2割を占める時代。
高齢の「おひとりさま」が増加。
少子・高齢化社会対策に関連させるためにも、個人の内面の問題まで掘り下げた。
それが「「令和の結婚観」企画。
この冒頭文の後、先述した2つの記事をリンク付きで紹介しているのです。
その意図は、当サイト「結婚家族.com」の方針と一致するものです。
少子化対策、少子化問題は、前回、前々回に、サイト開設企画的に以下の記事で取りあげました。
⇒ 「子育て支援は日本を救う」の真意を問う|柴田悠氏2書から読み解く少子化と財政問題 – 結婚家族.com
⇒ 「少子化対策の盲点」論をどう読むか|日経3回シリーズと柴田悠氏論考の比較と批判 – 結婚家族.com
後者の記事は、やはり日経掲載記事をベースにしたもの。
日経の担当者が、これからも追い続けるテーマですね。
なお、高齢化社会問題については、現在リニュアル、リスタート準備中のWEBサイト介護終活.com https://kaigoshukatsu.com の主要カテゴリーに設定。こちらで取りあげていきます。
日経が自ら生成AIでまとめた、正確性が保証されない「令和の結婚観」
ところで延長線上で調べていると、【β版Ask! NIKKEI】という括りの情報領域がありました。
⇒ Ask! NIKKEI (β版) – 「広く知る。深く知る。」新しいニュース体験
そこでは、日経が生成AIを活用し、自ら「令和の結婚観とはどのようなものですか?」と尋ね、それに応えていました。
「以下の内容は、日経電子版の記事を基に生成AIがまとめたものです。正確性は保証されません。生成されたコンテンツの権利等は日経に帰属します。」
とありました。
権利を侵害しないよう、「令和の結婚観の変化」の特徴を整理してみました。
・経済力の重視されるようになった。
・晩婚化と未婚率が上昇している。
・熟年離婚が増加している。
・多様な家族の形が顕在化し、認められるようになっている。
・結婚支援の在り方も多様になっている。
・シニアの結婚観にも変化が現れている。
・結婚自体も変化してきている。
・恋愛観の変化もみられる。
しかし、この傾向は、令和に入ってから起きた変化では決してなく、平成が進むに伴ってのもののはず。
加えて、正確性が保証されないとしている生成AIの整理では、少子化問題との関連性は、表現されていません。
「「結婚は当然」という考え方から、個人の自由な選択として捉えられる傾向が強まっている。」
この指摘も日経に限った、格別のもの、目新しいものでもありません。
こうした課題を、ほぼ永続的に追い続けるマスメディア。
どこに行こうとしているのでしょうか?
決め手となる提案・提言を打ち出すことができるのでしょうか?

メディア日経の「令和の結婚観・変化論」の罠と限界
仮に、昭和の時代の結婚観との違いを持ち出すことは、「ふてほど」のリライトのような気がしますし、まったく面白くないですね。
かと言って、日経の「令和の結婚観変化」説には、特段の新鮮味も、強烈な主張も読み取ることはできません。
結局、いつものように、決定的な帰着にたどりつくことはないのです。
焦点をぼかし、包括的に政府や行政の取り組みの甘さを指摘し、対策を求めているかのように。
となると、日経が固く守る「財政規律主義」が岩盤として立ちはだかるのです。
すると、社会的課題、社会問題とし、人々と社会の意識の変化を求めることに。
それは結局、すべては「自己責任」に帰することに向かわせるかのように思うのです。
ただこれは、日経に限った事ではなく、すべてのメディアに言えることです。
そして、すべての学者・研究者にも言えることでもあります。
人生100年時代の ”ライフステージ” の起点としての「結婚」
令和という時代にその結婚観が変化している、というのが日経記事のテーマでした。
それは、私と当サイトがテーマとしている「人生100年時代の結婚の在り方と特徴」と重なっています。
2つの生成AIに「令和の結婚観とこれからの課題」というタイトルを条件としたのは、その意図があったから。
その要約結果は、ほぼ「なるほど、そうだよな」と思えるもの。
可もなく、不可もない、メディア日経の問題提起・情報提供そのもの。
「結婚」は、それを望み、子どもを持つことを望む世代の人たちの希望実現のスタートです。
またそれは、少子化社会の進行の抑制に繋がる重要な選択行動と言えるでしょう。
結婚は、一つのライフイベント と表現することもあります。しかし、当サイトでは、一つのステージに立つ、ステージにある、という意味で捉えます。
結婚論を主テーマとする新設WEBサイト、結婚家族.com のプロローグの一つとして、本記事を位置付けています。
2025年5月11日から9つ目の記事。
ここまでは、過去他サイトに投稿した記事の改訂版を多く投稿してきました。
明日の10本目の記事迄を、助走期間として臨んできています。
少子化社会の加速・進展にどのように対処するかを考察し、対策を提案。望ましい行動を少しでも起こすことに繋がる。そうしたWEBサイト、個人メディアでありたいと考えています。
6月からは、新しい、まっさらな記事を、と考えています。
どうぞ、今後とも宜しくお願いします。

前回の記事に戻ります。
⇒ 「少子化対策の盲点」論をどう読むか|日経3回シリーズと柴田悠氏論考の比較と批判 – 結婚家族.com
コメント