子ども視点での家族の変化|日経「やさしい経済学:変わる家族のありかた」シリーズからー3
日経が2025年6月から7月にかけて9回シリーズで連載した古村聖(みづき)関西学院大学准教授に拠る「変わる家族のあり方」。
これをテーマに、ここまで以下の記事を公開しました。
第1回:変わる家族のかたちと経済学の視点|家族規模の縮小と「個人化」する家族関係を読み解く – 結婚家族.com
第2回:家族規模縮小の本質とは?「性別役割分業の衰退」と「家族機能の外部化」論への異議 – 結婚家族.com
本記事には、広告が挿入されることがあります。
はじめに
日経「やさしい経済学」シリーズ『変わる家族のあり方』の連載を読み解く第3弾です。
これまでの記事では、家族の平均世帯人数の減少、家族規模の縮小や、家族問題の焦点が「世帯」から「個人」へと移り変わってきた経済学の視点について考察してきました。
私は、その背後にある経済学の論理と、現実社会とのギャップについて、独自の視点から問いを投げかけてきました。
今回は、以下の連載の5回目と6回目にあたる小論をテーマに、さらに深く家族の変容、特に「子ども」をめぐる経済学的側面と夫婦間の意識のズレに焦点を当てます。
5.変わる家族のあり方(5)子どもが持つ経済的な側面 – 日本経済新聞 (2025/6/25)
6.変わる家族のあり方(6)子どもを巡る夫婦の意識のズレ – 日本経済新聞 (2025/6/26)
果たして、子どもを持つことの「便益」と「費用」という経済的な視点だけで、現代の少子化や家族のあり方を語り尽くせるのでしょうか?
そして、夫婦間の子育てや家事の分担状況が、子どもの数にどのように影響を与えるのか。
経済学が提示する仮説に、私たちの実体験や社会の現実を重ね合わせながら、その本質を考えてみたいと思います。

では順に見ていきます。
変わる家族のあり方(5)子どもが持つ経済的な側面 – 日本経済新聞 から。
【変わる家族のあり方(5)子どもが持つ経済的な側面】から
この小論では、家族規模の縮小、特に子どもの数の減少を経済学的な視点から分析しています。
まず、同小論を、生成AI、Geminiに要約してもらいました。
Geminiによる「子どもが持つ経済的な側面」要約
1)結婚と子どもの経済学的意義
結婚の動機の一つとして子どもを持つことを挙げ、それが減少する背景を「子どもの便益(メリット)」と「子どもの費用(コスト)」の観点から説明します。
分析の便宜上、子どもを持つことを結婚の中心目的と位置づけることで、その目的が薄れることが家族形成の動機喪失につながると考えます。
2)便益(メリット)の減少
かつて子どもは家業の手伝いや成人後の親への経済的支援など、経済的なメリットがありました。
しかし、公教育の普及、世襲制度の崩壊、公的社会保障制度の充実により、これらの経済的メリットは相対的に小さくなりました。
加えて、「子どもを持つことだけが幸せではない」という価値観の広がりも指摘されています。
3)費用(コスト)の増大
費用の側面では、女性の社会進出と賃金上昇に伴い、育児に時間を費やすことで失われる収入やキャリアの機会が増大したことを挙げます。
教育や職業訓練への投資リターンが増加することでキャリア追求のインセンティブが高まり、結果として晩婚化や第1子出産年齢の上昇が進み、生涯に持てる子どもの数が減少する傾向にあります。
教育費や住宅費の高騰も子育てコストを押し上げています。
4)経済的合理性と人口動態の変化
子どもは経済的合理性だけで産み育てるものではないとしつつも、これらの経済学的仮説が多くの実証研究で一定の説明力を持つことを強調。
医療技術の進歩による乳児死亡率の低下が、計画的な出産選択を可能にし、出生率低下や家族規模の縮小を後押しした要因の一つであるとも示唆しています。
小論の原文と要約から、私なりの意見・感想を整理してみました。
子どもが持つ経済的側面からの議論・分析がムリ筋
【やさしい経済学】欄における、家族経済学研究者に拠る小解説シリーズ。
そのため経済学的アプローチで家族や結婚、少子化問題の要因と対策などを展開しています。
そのため手法は、経済学視点でそれらの問題を考えるもの。
一般論的にも、少子化問題は、後述するように、経済学的に、経済的な課題として取り上げられます。
しかし、この小論でまず提示されたのが、子どもをもつことでの便益(メリット)とその便益を減殺させるコスト(デメリット)視点でのもの。
家族規模縮小問題を主題の一つとしているシリーズとしてはやむを得ないかもしれなかったですが、メリット・デメリット比較計量法では、的確な議論ができないでしょう。
子を持つことが結婚目的という仮説自体がムリ
そもそも、経済的メリット・デメリットを論じるために、「子どもを持つことが結婚の目的」と仮説ながら、条件としたこと自体ムリがあります。
そのムリやり設定された「子ども」について、個々の家族においての便益とコスト、両面で、行動への影響度を計ってみようというわけです。価値やコストを価額で表現できない要素・要因が結婚や子どもを持ち、養育することにあることを無視してしまうムリ。
強引ですし、非合理的です。
果たして、経済的合理性がそこにはあるのでしょうか。
子を便益の手段・道具と見ることにも自ずとムリが
そもそも、子どもを持つことで経済的な便益、便利さ、有益性を得ようとする人、親がどれだけいるのか。
経済学的に実証された研究はあるのでしょうか。
彼らの「実証された」という証拠は、1件でも実例があれば、その範疇に含めるレベルと考えてしまいます。
心理的・心情的・情緒的要素要因は、プライスレス。
経済学の領域とは異なります。
コストの増大が家族規模縮小要因とすることの矛盾
仮にコスト要因の比重が大きく、重かった場合、家族規模縮小に直接的に影響するのか。
そうであれば、前々回の、種々の家族ケアや家事に関わるコスト低下が、家族規模縮小に影響したという論説と矛盾します。
少なくとも、これらのコスト低下が、子どもの養育のためのコスト増大と一部であっても相殺されるはず。
想定される相殺レベルの試算・分析を行うべきでしょう。
なお、元々子どもを持たない前提での結婚については、家族規模縮小というテーマにおいては、種々議論する必要はないと考えます。
単純に、子どもを持たない夫婦という家族形成であり、その割合を把握すれば済む話ですから。
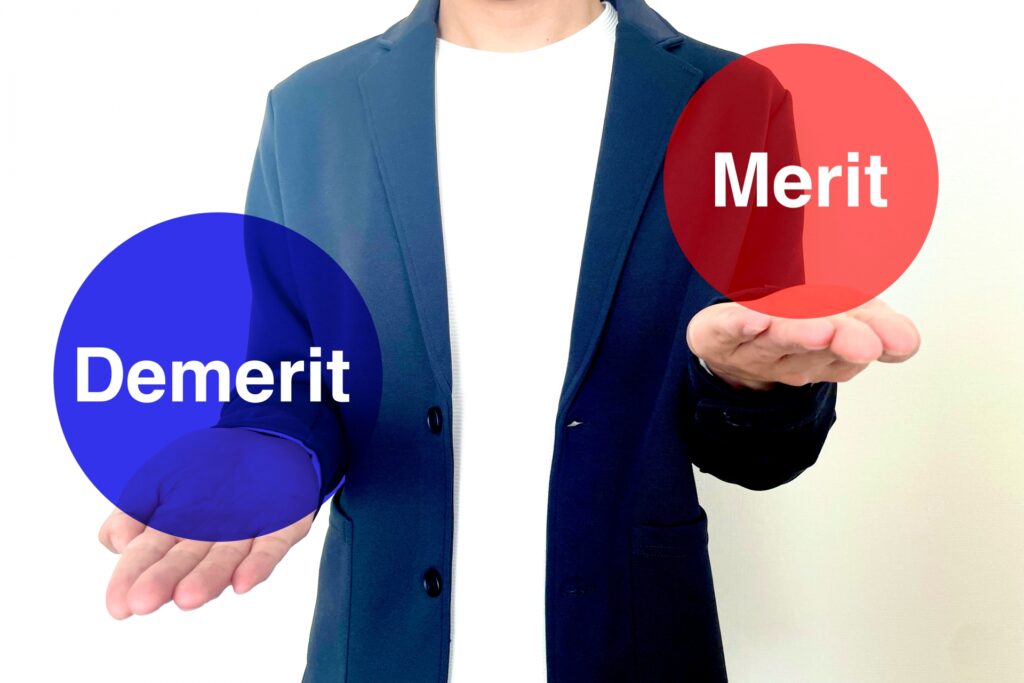
次に、変わる家族のあり方(6)子どもを巡る夫婦の意識のズレ です。
【変わる家族のあり方(6)子どもを巡る夫婦の意識のズレ】から
同じように、当小論を、Geminiに要約してもらいました。
Geminiによる「子どもを巡る夫婦の意識のズレ」要約
この小論では、女性の社会進出と出生率の関係性について、一概に負の関係ではないことを指摘し、育児や家事の夫婦間での分担状況が子どもの数に影響を与える可能性を考察しています。
1)子どもの数を決める夫婦の合意
子どもの数は夫婦の合意によって決まり、特に女性の希望が少ない方に反映されやすいという考え方を提示します。
男性がもう1人子どもを希望しても、女性が望まなければ、その希望は子どもの数に反映されにくいと考えられます。
2)国際比較から見る育児分担と出生率
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの研究を引用。
育児負担が女性に偏っているロシアや東欧では、女性が次の子どもに否定的で出生率も低い。一方、育児・家事分担が進むフランスやノルウェーでは、子どもに対する夫婦の希望差が小さく、女性の労働参加と出生率がともに高い水準で維持される傾向にあると説明しています。
3)日本における「チャイルドペナルティー」
日本は上記の研究対象外ですが、時間配分の男女差が大きいことは知られています。
出産・育児に伴う女性の社会的・経済的な不利益である「チャイルドペナルティー」の研究が進んでいる。
日本の大手製造業の正社員を対象とした分析では、出産後10年間で男女間の所得差が55ポイント拡大し、その後も影響が続くことが示されています。
このことから、夫婦のどちらか一方に子育て負担が偏れば、負担の大きい側が次の子どもに消極的になる可能性は十分考えられます。
4)「個人」への注目で新たな要因解明へ
小論は、子育ての金銭的負担や結婚・出産時期の遅れも出生率に影響するものの、世帯内の個人一人ひとりに注目することで、出生率低下の新たな要因が解明できると締めくくっています。
以上の要約と小論原文からの私の整理が以下です。
家族規模縮小の要因に、女性が子どもの数決定権を持つ説のムリ筋
ここまでの6つの小論の中で、最も取って付けたようなムリ筋を感じてしまう内容でした。
女性の社会進出が先行して顕著な北欧など一部の国では、少子化はないと紹介するのも常套です。
しかし、それらの国々でも、揺り戻しはあり、右肩上がりで少子化を克服し続けているわけではありません。
新しい観点か古典的議論か|「子どもの数の決定権は女性に」説の経済学的意味とは?
「子どもの数を決めるのは女性の方」と論じるのは、新しい見方なのか、それとも古典的な見方なのか。
経済学的にはどうなのでしょう。
先の便益とコストの比較計量方式においても、女性の方が「コスト」意識が「メリット」を上回っているということになってしまいます。
ここで持ち出してはいけないかもしれませんが「母性」も「コスト」意識には勝てない、ということになりそうです。
挙句に、「チャイルド・ペナルティー」要因を用い、社会と企業サイドの責任を上乗せしています。
出生率低下の新たな要因解明は、世帯内の個人一人ひとりに注目すれば可能か?
あまりにも小論に費やすことができる紙数・文字数に制約があるため、やむなく、「もちろん子育ての金銭的負担や結婚・出産時期が遅くなっていることも、出生率に影響するでしょう」と付け加えています。
その上で「しかし、世帯内の個人一人ひとりに注目すれば、出生率低下の新たな要因が解明できるかもしれません。」と結んでいます。
本小論の初めに「個人化」をキーワードに設定していました。
その「個人」に、出生率低下要因の解明のために注目すれば、というのです。
これは、ギブアップしたに等しい結び方です。
残念というか、想定されたこととすべきか、微妙なところです。

今回の、子どもをテーマとした2つの小論をまとめて、簡単に振り返ってみました。
少子化要因分析と対策の従来型経済学アプローチからの脱却を
シリーズの主テーマである「家族規模縮小」の根本的な要因は、間違いなく少子化、合計特殊出生率の著しい低下にあります。
その要因あるいは背景を「子どもが持つ経済的側面」で分析することは決して間違いではありません。
しかし、その中で、「便益」をまさにコストと対比させて、経済的要素のみで計量評価することにはムリがあります。
心理的・情緒的、あるいは種の保存という原始的・本能的な人間としての営みの要素を、計数・計量かせずに論じることは、極めて不自然なこと。
いくら経済学といえど、それは傲慢なことと考えます。
怠慢というべきかもしれません。
経済学者や経営者の常套、社会経済的貢献・労働資源としての子どもの便益論もムリ
本小論ではなぜかなかったのですが、経済学者や経営者が必ず主張する、少子化問題の最大の要素・要因。
それは、少子化が、労働資源が減衰し、経済成長を不可能にし、社会を維持することを困難にすること。
また別の面からは、子どもの教育への投資が、こうした経済成長や社会貢献に大きく寄与することが証明されている、というのも経済学者の常套論説。
こうした議論も、子どもを持ちたい・持ちたくないと悩み、考える当事者の意識とは無縁・無関係のものです。
子どもを持つ持たないをコスパ論化する愚
子どもを持つことを、「便益」と「コスト」を持ち出して、対立選択要素化し、判断要素・行動決定要素とする。
言い換えれば、子どものコスパ論の対象としているわけです。
それが経済学と言うならば、愚の骨頂、愚学の骨頂でしょう。
子どもをめぐる経済学視点でのメリット・デメリット論からの転換法
経済学者に拠る家族問題・結婚問題・少子化問題については、端的な例として、以前も紹介しましたが、当サイトの以下の記事を紹介しています。
⇒ 「子育て支援は日本を救う」の真意を問う|柴田悠氏2書から読み解く少子化と財政問題 – 結婚家族.com
一般的に、EBPMを主張する彼らの経済学的手法には、ムリがあります。
実証のレベルや質に明確な基準があるわけではなく、構成比や貢献度が数字で示されても、それが、子ども一人ひとりの実数でカウントされ、実在することになったものでは決してないのです。
結局、今回の小論の結論としての「個人」を一人ひとり見ていくことを提示するしかなくなる。
本論を執筆した若手研究者は、このことをどう感じるでしょうか。
では、私のその限界のある手法からの提案をできるのか。
もちろん、ムリです。
ただ申し上げておくべきは、ここに社会学的なアプローチを統合させて、議論し、分析提案作業を行うべきこと。
また、経済学アプローチにおいては、財政・財源問題も最終的提案・提言時に必ず添えること。
以上です。
但し、社会学者においても、その作業は不十分で、財政・財源問題には踏み込まず、経済学・経済的アプローチ考察においては、どこか他人事風な処理に終わり勝ちです。
結局、最終的には、政策提案・提言のあり方、内容に行く着くのですが、本小論では、最終回9回目でのテーマとしています。
この9回目の小論と全体の総括を一体とした記事を予定しています。
但し、その前に、もう1回、本稿シリーズがあります。
当初期待をもって始めたシリーズでしたが、ここまで、批判めいたことばかり述べて来ました。
次の2つの小論は、介護問題と単身問題に焦点を当てた、以下の記事を取り上げます。
7.変わる家族のあり方(7)弱まる家族機能と親の介護 – 日本経済新聞 (2025/6/27)
8.変わる家族のあり方(8)増える単身世帯を待つリスク – 日本経済新聞 (2025/6/30)
果たしてどうなるでしょうか。

なお、当該の日経記事へのリンクを貼っていますが、同紙の電子版は有料読者だけがアクセス可能であることをご了承ください。
コメント